こんにちは、絶賛育児中のしろまるです。
私はフリーランスなので、育休はありません。そのため、生後2ヶ月のころから仕事を再開しました。
赤ちゃんがまだ小さいうちは、授乳・おむつ替え・寝かしつけの合間に作業をする日々で、正直言ってかなりハード…。
そんな中でも「これがあって本当に助かった!」と思えるアイテムを、Amazonを中心にまとめました。
同じように両立に悩むママ・パパに届きますように。
1. おむつ替えの効率アップグッズ
ベビーケアマット&立ち高さのおむつ台
おむつ替えするために地面に座ったり立ったりするのって、地味にストレスだし、体力を奪われます。
IKEAのベビーケアマットと立ち高さのおむつ台を組み合わせることで、立ったままおむつ替えが可能になり、腰への負担が軽減されます。

2. 入浴・沐浴関連
沐浴剤(スキナベーブ)
生後2ヶ月ですが、首が座っていないのが怖くてまだ沐浴しています。
スキナベーブはお湯に入れるだけで洗浄・すすぎが省けるので、忙しい在宅ワーク中でも時短になります。
赤ちゃんの肌にも優しく安心です。
3. 眠らせる&リラックスさせるアイテム
ホワイトノイズマシン
泣き止まない赤ちゃんを落ち着かせたい時に重宝。
ノイズ音が「音の壁」を作ってくれるので、生活音もカバーしてくれます。
ホワイトノイズで寝つきがスムーズになり、リモート会議前でも焦らず対応できます。

4. おもちゃ・遊びグッズ
オーボール
0歳から使える知育玩具です。
赤ちゃんがつかみやすく、カシャカシャ音も楽しいので飽きません。
私は家用と外出用で2個持っていて、作業中も安心して遊ばせられました。
有名なプーメリーも良いですが、オーボールは値段がお手頃なので試しやすいですね。
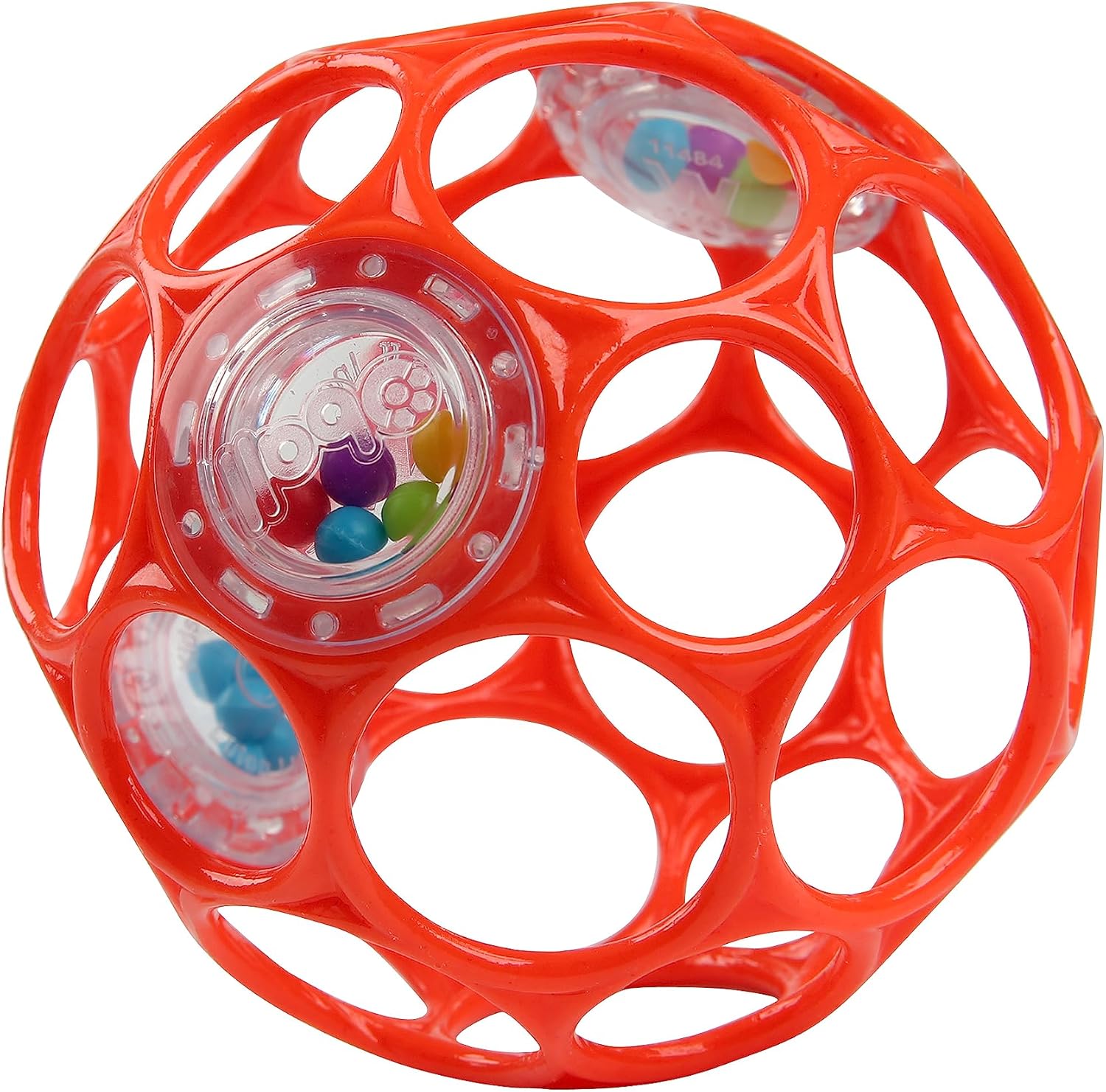
5. ケア&安心グッズ
ベビーカメラ(モニター付き)
赤ちゃんの動きをモニターし、動きが少ないとアラームで通知してくれるベビーカメラは、安心して作業に注力できます。
作業中に赤ちゃんが別室で寝ている時も、映像と音で様子を確認できる安心感があります。
動きや音を検知して通知してくれるタイプだとさらに便利です。
CuboAi スマートベビーモニターは、見た目も可愛くて癒されます。
ベビーサークル(プレイペン)
ちょっと席を外したい時や仕事に集中したい時に、赤ちゃんを安全に過ごさせられるスペースになります。
折りたたみ式なら省スペース収納も可能です。
リビングで近くに置けて、姿が見える安心感がありますね。
体動センサー(ベビーセンス・Sense-Uなど)
夜間に赤ちゃんの動きをモニターして、動きが少ないとアラームで通知。
安心して作業に集中できます。
ベビーモニターは少し高くて、なかなか手を出せないよという方、子どもの側で仕事はできるけど、乳幼児突然死症候群が心配という方にもおすすめ。4000〜5000円くらいで手に入ります。
20秒間体動がなければアラート音がなります。音もそんなに嫌な音ではないです。
音はそこまで大きくないので、別室で扉を閉めて使用する場合は、アラーム音が聞こえない可能性が高いので注意。
センサーをおむつに挟むだけなので、とっても簡単です。
夜も安心して寝ることもできるので、ママの心配も少し減りますね。

ハンズフリー抱っこ紐
「どうしても抱っこじゃないと泣いちゃう」時の救世主。
両手が空くので、メール返信や資料整理くらいなら十分できます。
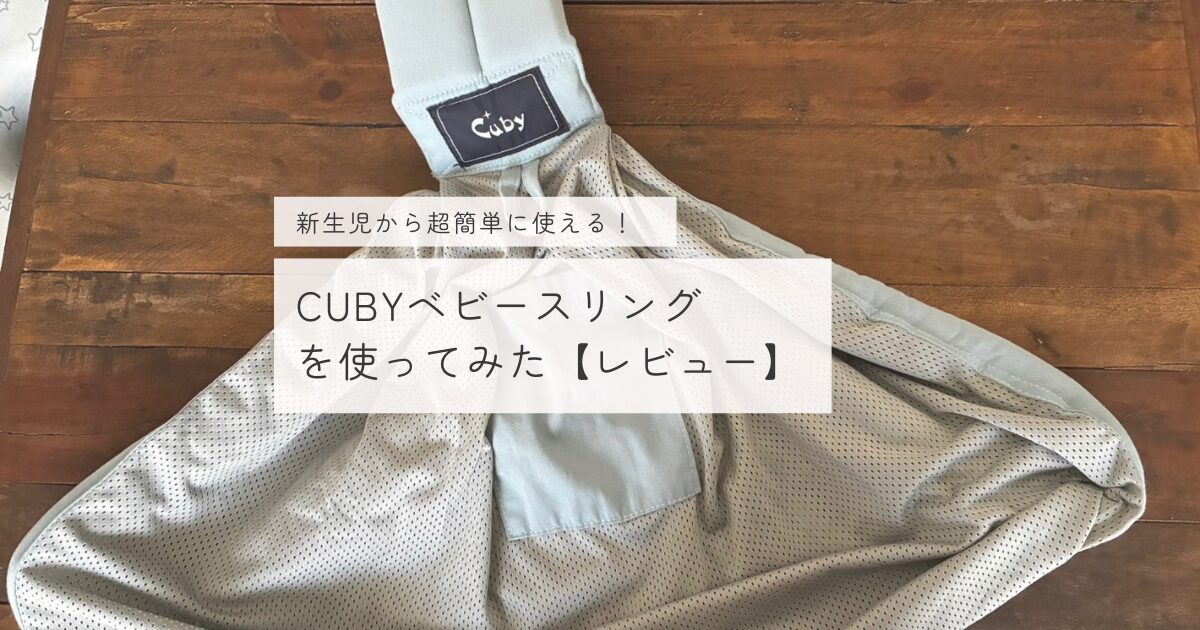
6. ミルク・授乳の準備時短
哺乳瓶は大きめ、複数本持ちがおすすめ
洗う回数が減るので時短に。
私は4本持ち+スチーム消毒器でまとめて消毒していました。
今は電子レンジ除菌が安全面の観点から禁止となっているので、ピジョンの哺乳びんスチーム除菌・乾燥器はおすすめです。

粉ミルクは「キューブ」や「スティック」を活用
計量不要でお湯にポン!
計量の手間がなく、外出先でもサッと作れるのが最大のメリット。
キッチンでもバッグでもすぐ取り出せて、忙しい朝や夜中の授乳がスムーズになります。

完ミか混合なら「液体ミルク」も検討
災害時の備蓄だけでなく、外出時や帰宅後すぐに授乳したい時にも重宝します。
開封して哺乳瓶に移すだけなので、時短効果は抜群です。
まとめ:フリーランスでも工夫次第で両立は可能
生後2ヶ月ごろは、まだまだ授乳・おむつ替え・寝かしつけのサイクルが本当に大変。
でも、便利グッズを活用するだけで「気持ちに余裕」が生まれます。
私自身も「これがなかったら回らなかった…」というアイテムばかり。
フリーランスのママ・パパもぜひ取り入れて、在宅ワークと育児の両立を少しラクにしてみてください。

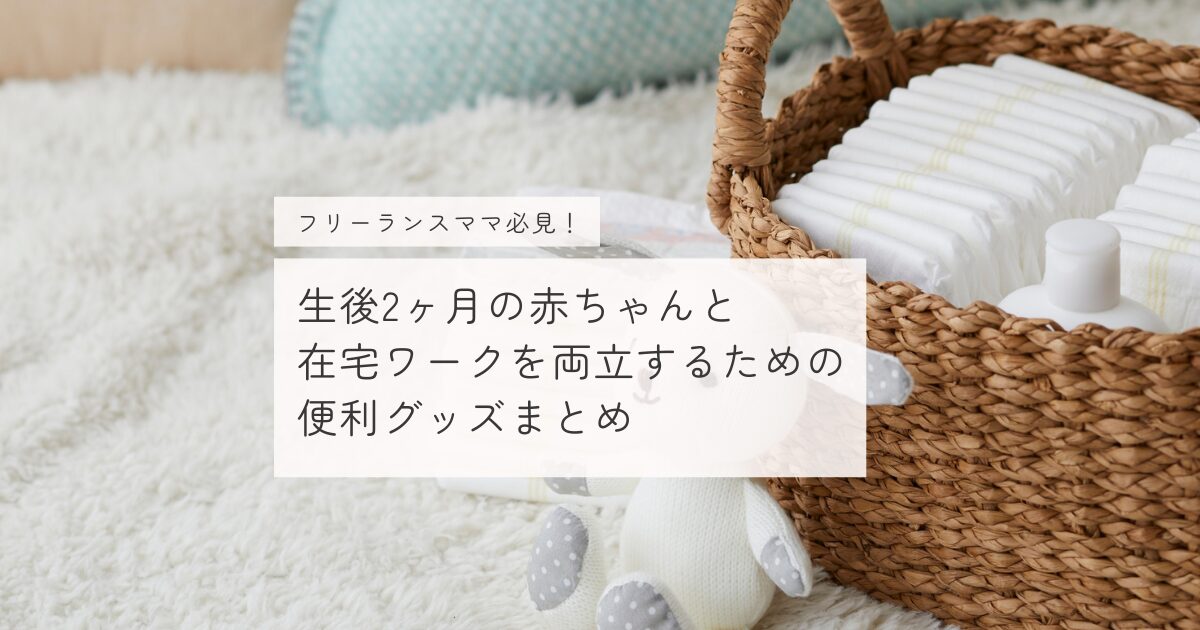



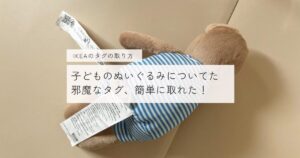
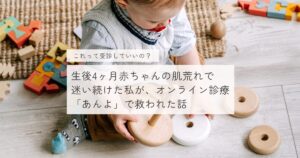
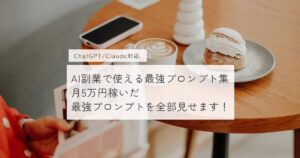
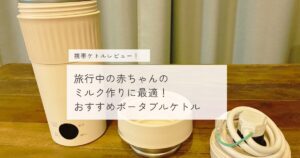



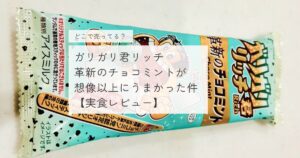
コメント